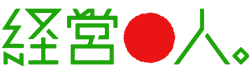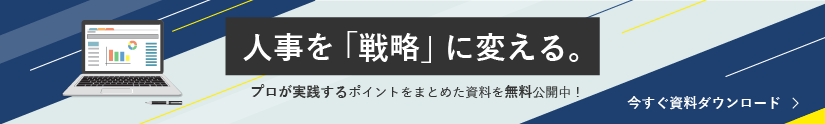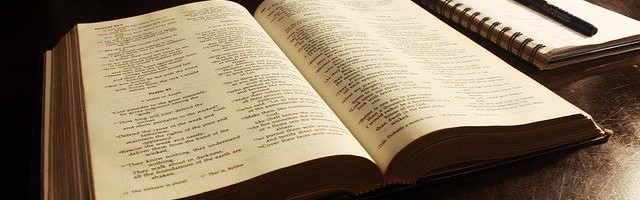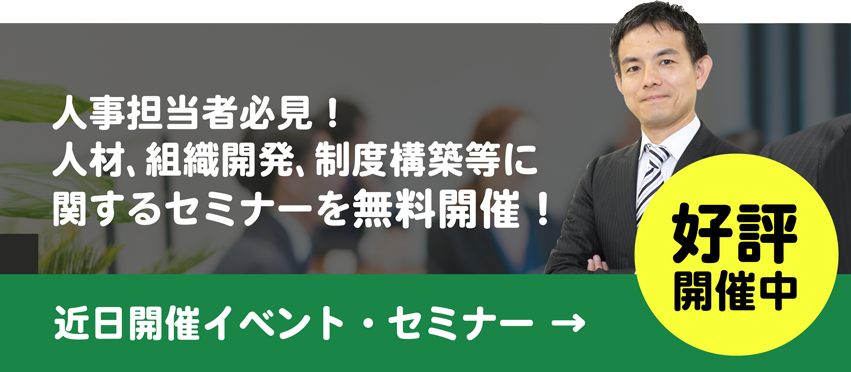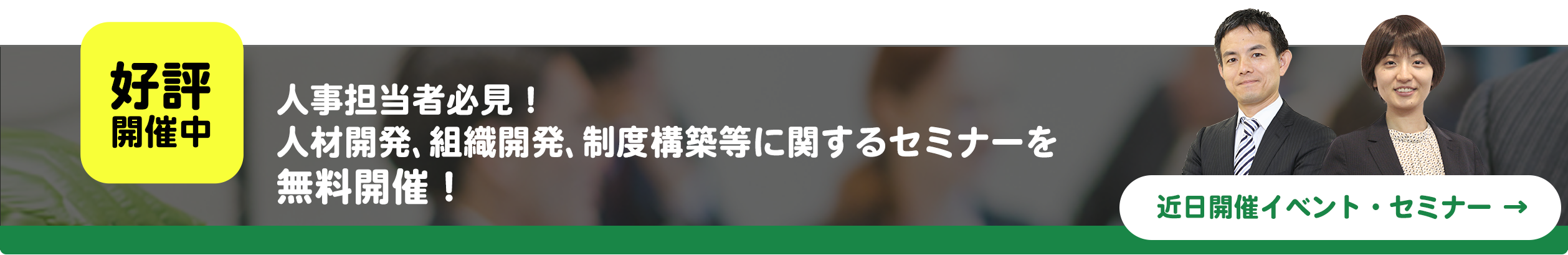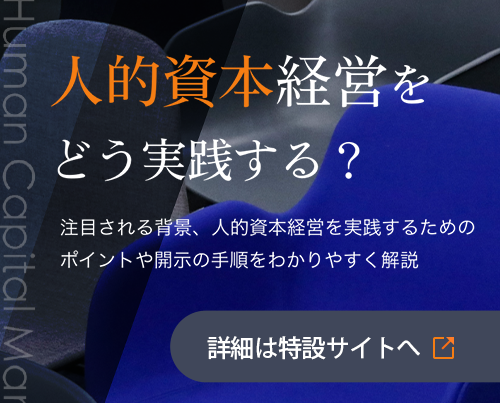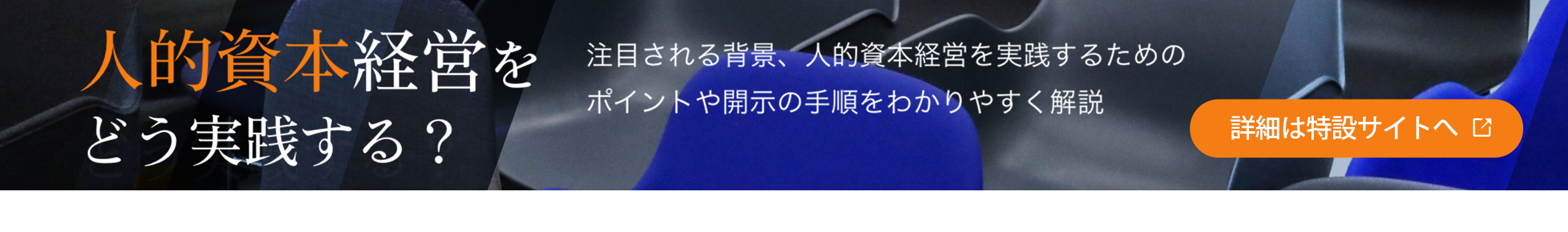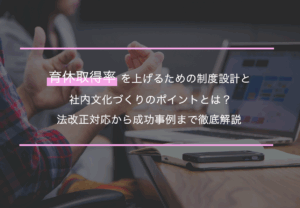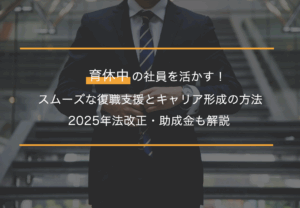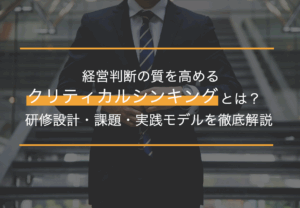人事の基本用語である「コンピテンシー」。あなたは意味や定義を人に説明できますか?人事では当たり前のように使われる言葉なので、いまさら人には聞けないという方も多いのではないでしょうか。打ち合わせで「コンピテンシー」という言葉がでてきたら、ついついわかったフリをしながらうなずいてしまいますよね。そこで今回は「コンピテンシー」の意味と定義から実際の活用方法までを詳しく解説します。

コンピテンシーとは?
ビジネスパーソンであれば、一度はコンピテンシーという言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか。コンピテンシーとは、どのような意味なのか改めて確認してみましょう。
コンピテンシーの意味と定義
コンピテンシー(Competency)はもともと英語で「能力」を意味する単語です。特に仕事における重要なスキルを意味しています。そこから転じて、ビジネスパーソンに求められる能力や資質を表すようになりました。ちなみに、コンピテンシーは単に「能力」だけを意味する言葉ではありません。また、知識やスキルなどのように学習を通じて短期的に獲得されるものでもありません。コンピテンシーは、特定の業務で高い業績や成果を出すために必要な知識や技術、資質を総称した行動特性と定義されます。
コンピテンシーの誕生と歴史
コンピテンシーは、ハーバード大学のデイビッド・マクレランド教授によって1970年代に提唱されました。マクレランド教授は、学歴やIQレベルが同じ外交官の業績が異なることに注目して、なぜ業績に差が出るのかを研究しました。その結果、高業績を出すための知識や技術、人間的特性を含む幅広い概念としてコンピテンシーを発表したのです。その後、マクレランド教授はマクバー社を設立し、あらゆる業界や業種で通用するコンピテンシーの調査を進めました。その後、1990年代にライル・M. スペンサーとシグネ・M. スペンサーによってコンピテンシー・ディクショナリーとして幅広い業種・業界で適用可能なコンピテンシーの一覧がまとめられ、今日ではコンピテンシーの概念が世界中の企業で人材マネジメント用語として定着しています。

コンピテンシーが人事で活用される理由
コンピテンシーの概念がここまで世界中で活用されているのはなぜなのでしょうか。その理由を考えてみましょう。
人材要件を設定したい
採用活動で人材要件を設定したい企業でコンピテンシーの考え方が活用されています。どの企業の人事担当者も、優秀人材を採用することを日々考えています。優秀人材を採用するには、人材要件の設定が欠かせません。
人材要件とは、その仕事に求められる能力、スキル、知識を定義したものです。人材要件を適切に定義したうえで、要件に当てはまる人材を採用できれば採用活動は成功と言えるでしょう。しかし、人材要件の設定は簡単なことではありません。その仕事で成果を上げるための要素を因数分解したうえで、成果に結びつく要素の優先順位を決める必要があります。企業によっては数百種類以上もある仕事の人材要件を決めるのは、大きな負担になります。
また人材要件を細かく設定したところで、要件に合う人材が採用市場にいない可能性もあるでしょう。そこで職種・業種を超えて幅広く適用可能なコンピテンシーをもとに人材要件を設定する方法が用いられています。コンピテンシーは汎用的な考え方であるため、ポータブルスキルを簡単に定義可能なのです。特に雇用の流動化が激しい欧米では、求人票の作成の際にほぼ必ずスキル・コンピテンシーの記載があります。
これまでメンバーシップ型雇用制度が中心だった日本ではコンピテンシー要件が記載されている求人票は多くは見かけませんでした。しかし、ジョブ型雇用制度が普及する今後の日本ではコンピテンシーをもとに人材要件を設定する企業も増える可能性があると考えられます。
人材育成の効果測定をしたい
コンピテンシーは、人材育成の効果測定をする時にも活用されます。企業にとって人材育成は大きな投資である一方で、人材育成の効果を確認するのは簡単なことではありません。そこで企業ではコンピテンシーの習得状況や伸長度合いを人材育成の効果測定として活用しています。
そもそも、基本的な人材育成の考え方は目標とする能力や知識、スキルを獲得するための教育を行うことです。例えば、企業の階層別教育では、目標となるコンピテンシーを設定して、コンピテンシーの習得や向上を目的に研修を実施しています。コンピテンシーの習得度合いは、大きく2つの方法で効果測定されます。
1つ目は職場でのコンピテンシーの実践状況を上司が確認する方法、2つ目はアセスメントによって確認する方法です。職場で上司が部下のコンピテンシーの実践状況を把握するためには、上司がコンピテンシーについてよく理解していなければなりません。そのためWEB上などでコンピテンシーに関するテストを行うアセスメントが最も簡単な測定方法と言えます。実際に大手企業の多くは、研修前後にコンピテンシーアセスメントを行って従業員のコンピテンシーを確認しています。
コンピテンシーの活用目的
実際に企業の現場では、コンピテンシーは、どのような場面で活用されるのでしょうか。
優秀人材の見極め
コンピテンシーの活用方法として最もよく使われている目的が、優秀人材の見極めです。現代社会は、人材獲得競争と言われるほど人材によって企業業績が大きく左右されるようになってきています。その背景には、新型コロナウィルスの影響や、AIやロボットに代表されるテクノロジーの進化といった社会環境変化の激化があります。
変化の激しい現代では、環境変化に柔軟に対応しながら短期的に成果を上げる必要があるでしょう。そのため、特定の技術を持った人材やどんな状況でも成果を出せる優秀人材がどの企業でも強く求められているのです。
一方で、人材獲得において「優秀」の定義は難しいものです。企業の人事担当者に対して「御社の『できる人』はどのような人材でしょうか?」と質問をしてみると、各企業ともに全くバラバラな答えが返ってきます。また、企業内部でも「優秀人材」の定義が役員と人事担当者、現場の社員との間で認識が全く異なる場合があります。
コンピテンシーは、世界的に利用されている概念です。そのため、「優秀人材」の認識を合わせ、明確に定義するためのツールとして優秀人材の獲得に大いに役立っています。
社員の能力開発
もう一つの目的が社員の能力開発です。多くの日本企業では、社員に求められる能力をコンピテンシーの概念をもとに整理しています。自社独自のコンピテンシーモデルを作成してそれをもとに教育や研修を行うことが人材育成の中心的な手法です。コンピテンシーモデルは、多くの場合、4~5項目から構成される行動特性と、行動特性の習熟段階を定義した行動段階から構成されます。
行動特性にはその企業の社員に求められる能力が列挙されています。例えば、「問題解決力」、「目標達成志向」、「創造性」などです。こうしたそれぞれの項目に対して、習熟段階が3段階から5段階で設定されています。
例えば「問題解決力」であれば、1段階目は「上司の指示に従って問題解決を行う」、2段階目は「自力で問題解決できる」、3段階目は「自ら問題を発見して解決できる」といったように、習熟度のレベルが具体的に定義されているのです。企業はこうした行動特性と習熟段階をもとに階層別教育を行うだけでなく、人事評価にもコンピテンシーを取り入れて評価を通じた能力開発を行っています。

コンピテンシーの類似概念
コンピテンシーは世界中で普及している概念です。一方で、コンピテンシーと類似した概念もよく見かけるのではないでしょうか。それぞれの概念とコンピテンシーとの違いについて考えてみましょう。
コア・コンピタンス
コンピテンシーと混同しやすい概念の一つに「コア・コンピタンス」があげられます。コア・コンピタンスは、一言でいえば「競合他社に追随を許さない自社ならではの価値」と定義されます。ロンドン・ビジネススクールの客員教授だったゲイリー・ハメルとミシガン大学ビジネススクール教授のC. K. プラハラードの2人の経営学者によって1990年に紹介されました。
ハメルとプラハラードは、コア・コンピタンスを「顧客に対して、他社には提供できないような利益をもたらすことのできる、企業内部に秘められた独自のスキルや技術の集合体」と定義しています。例えばソニーは、圧倒的な技術力とブランド力で長年にわたって優れた製品を世に送り出してきました。また、ヤマト運輸は非常に細かい単位で宅急便センターを設置することでいつでも荷物をやりとりできる仕組みを構築しています。このように優れた企業には、独自の強みがあるのです。
なお、コア・コンピタンスを見極めるには5つの要素を考える必要があるとされています。
- 模倣可能性(Imitability):その強みは他社に模倣される可能性があるか
- 移動可能性(Transferability):その強みは他社に移動、移転できる可能性があるか
- 代替可能性(Substitutability):その強みは他のものに代替できる可能性があるか
- 希少性(Scarcity):その強みは希少か
- 耐久性(Durability):その強みには耐久性があるか
こうした5つの要素をなるべく多く備えた強みがあれば、企業は独自の強みをもとに経営を行うことができるのです。同時に企業はコア・コンピタンスを維持、あるいは成長させるために積極的に投資すべきだとされています。
以上のように整理してみると、コア・コンピタンスはコンピテンシーと全く異なる概念だと理解できるでしょう。コア・コンピタンスは企業の組織全体に適用されるのに対し、コンピテンシーは人材の能力や資質を定義したものです。組織が成果をあげるためのコンピテンシーがコア・コンピタンスと言えるかもしれません。
ケイパビリティ
コア・コンピタンス同様に、コンピテンシーと類似する言葉としてケイパビリティがあります。ケイパビリティは、英語で「能力」「才能」「素質」を意味する言葉です。しかし、経営用語として「ケイパビリティ」を使う場合は企業の成長の源泉となる組織的能力や強みを意味します。
一般的に日本のビジネスシーンでケイパビリティが使われた場合、この組織的な力であるケイパビリティを指すことが多いでしょう。企業は差別化が難しい状況の中で、ケイパビリティを高めることで競争優位の状態を生み出すことができます。コア・コンピタンスはある特定の分野に集中した強みを意味するのに対して、ケイパビリティは組織横断的な企業の能力であることが違いです。また、コア・コンピタンスと同様、ケイパビリティは組織の能力であるため、個人の能力を意味するコンピテンシーとは異なる概念です。
コンピテンシーの導入と活用方法
コンピテンシーの概念については理解いただけたのではないでしょうか。では実際にコンピテンシーを導入するにはどうすればよいか、最後にご紹介します。
コンピテンシーの導入方法
ここまでご説明の通り、コンピテンシーは「高業績をあげるための能力・知識・スキル・資質」と定義されます。つまり、コンピテンシーを導入するにはその企業あるいは職務において「高業績をあげるための」能力や知識、スキル、資質を考える必要があるのです。コンピテンシーを定義するには、4つの方法があります。
実在するハイパフォーマーをモデルにする
多くの企業で取り入れられているのが、社内で実際に高業績をあげているハイパフォーマーをモデルにしてコンピテンシーを作成する方法です。ハイパフォーマー数名にインタビュー調査を行い、自社のハイパフォーマーに共通する行動特性を明らかにしていきます。
また、ジョブ型雇用制度の場合は、その職務におけるハイパフォーマーにインタビュー調査を行い、職務におけるコンピテンシーを定義します。実在するハイパフォーマーをモデルにすることで、再現性の高いコンピテンシーを作成できることがメリットです。一方であくまでも現状のハイパフォーマーをモデルにするため、将来的に経営環境が変わった場合、コンピテンシーを作り直さなければならないというデメリットもあります。
求めるコンピテンシーをモデルにする
社内にハイパフォーマーがいない場合や、新たな経営環境に適応するコンピテンシーを作成する場合は、社員に求めるコンピテンシーをモデルとして作成します。社員に獲得してほしい能力や知識、スキルをコンピテンシーとして整理するのです。
求めるコンピテンシーを定め、同時にコンピテンシー獲得のための社員教育を整備すれば、コンピテンシーを獲得できます。新たな環境に対応できるとともに、社員の能力を向上できるメリットがあります。一方で、あまりにも社員の現状からかけ離れたコンピテンシーを設定してしまうと、誰もそのコンピテンシーを獲得できなくなってしまうデメリットがあるでしょう。
①と②を組み合わせて実現可能なコンピテンシーモデルを作成する
なるべく実現性が高いコンピテンシーモデルをつくりたい一方で、社員の能力向上も実現したい場合は、実在するハイパフォーマーのコンピテンシーと求めるコンピテンシーを組み合わせたコンピテンシーモデルを作成します。この方法であれば、現在の業務で高業績を上げながら社員の成長を両立することが可能になるでしょう。
コンピテンシー・ディクショナリーを活用する
もっとも簡単なコンピテンシーモデルの導入方法は、コンピテンシー・ディクショナリーを活用する方法です。コンピテンシー・ディクショナリーは、業種や業界、そして職種にあわせたコンピテンシーの一覧です。
人事系コンサルティング会社に依頼して使用料を支払えば、すぐにでもコンピテンシーを導入できます。導入がスピーディーに実現でき、社外労働市場に通用する汎用的なコンピテンシーを導入できる一方で、決して安くはないコストが発生することがデメリットです。
また、コンピテンシー・ディクショナリーはあくまでも汎用的なものなので、自社に最適化されたものではありません。そのため、より自社にあったコンピテンシーを作成したい場合は、コンピテンシー・ディクショナリーを活用する方法は適していないと言えるでしょう。
コンピテンシーの活用方法
自社独自のコンピテンシーモデルを作成できたら、実際にコンピテンシーを活用しましょう。コンピテンシーモデルの活用シーンは、大きく3つあります。
採用面接での活用
コンピテンシーモデルに基づいて採用面接を行えば、自社が求める人材に合致した人材を高い精度で獲得できます。面接では、コンピテンシー項目に沿って応募者にインタビューを行います。合致するコンピテンシーが多いほど、自社に合った人材を獲得できるでしょう。一方で、コンピテンシーモデルにこだわると同質的な人材ばかりが集まってしまうデメリットもあります。あるいは能力が高くても性格的に難色がある人材を採用してしまうかもしれません。人材の多様性や人間性を重視したいのなら、コンピテンシーモデルを基本としながらも面接以外に性格検査を実施するとよいでしょう。
人材育成での活用
コンピテンシーは人材育成で大きなメリットを発揮します。ここまで何回かご説明したように、新たな能力を獲得したい場合や、社員教育の効果測定を行いたい場合など、人材育成ではコンピテンシーモデルの活用シーンが多くあるのです。特に新入社員の育成や、階層別教育で上位の職位や役割を担うための能力獲得でコンピテンシーモデルを活用した育成手法は大きな効果が期待できるでしょう。
また、ジョブ型雇用制度を導入する場合も、職種ごとのコンピテンシーを予め定義しておけば、その職務におけるコンピテンシーを向上させるための育成施策を実施できます。コンピテンシーはある意味、使い古された概念ではありますが、人材育成においてはまだまだ活用できる概念といえるでしょう。
人事評価での活用
多くの企業では、コンピテンシー評価が導入されています。業績を評価するだけではなく、業績につながる行動を評価するためです。少し古い情報になりますが、重電機大手のGEでは業績評価よりもコンピテンシー評価を重視してきました。どんなに高業績を挙げた人材でも、コンピテンシー評価がよくなければ昇進することはありませんでした。
コンピテンシー評価は、リーダー候補となる人材を見極める方法としてかなり有効です。高業績を挙げる人材の中には、部下指導などのマネジメントが苦手な人材がいます。一方で低業績者でも、人を動かすことのできる人材はいるものです。いわゆるプレーヤーとマネジャーは求められるコンピテンシーが異なるため、コンピテンシー評価は将来のリーダー候補を見つける方法として多くの企業で導入されています。
まとめ
今回は人事の基本用語であるコンピテンシーについてご紹介しました。コンピテンシーは、人事関係者のみならず、ビジネスパーソンにとって当たり前すぎるほど普及している概念です。一方で改めてコンピテンシーについて考えてみると、特に人材育成や人材の見極めにおいて有効な考え方であることがわかります。ジョブ型雇用制度が普及しつつある現代の日本では、コンピテンシーは改めてその価値を見直されてもよいのではないでしょうか。
この記事を読んだあなたにおすすめ!