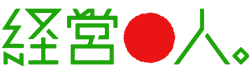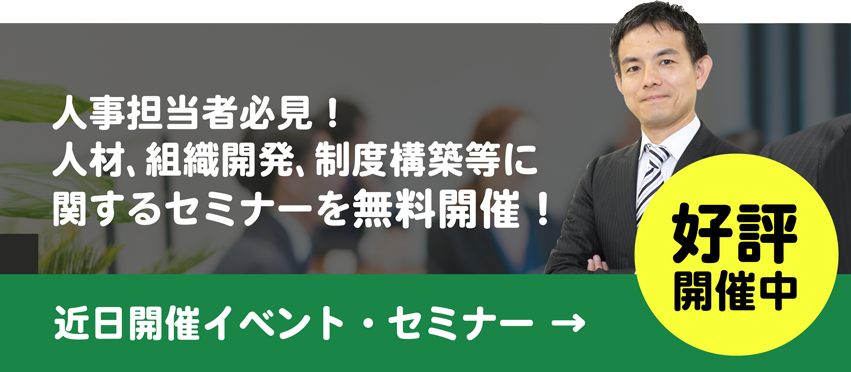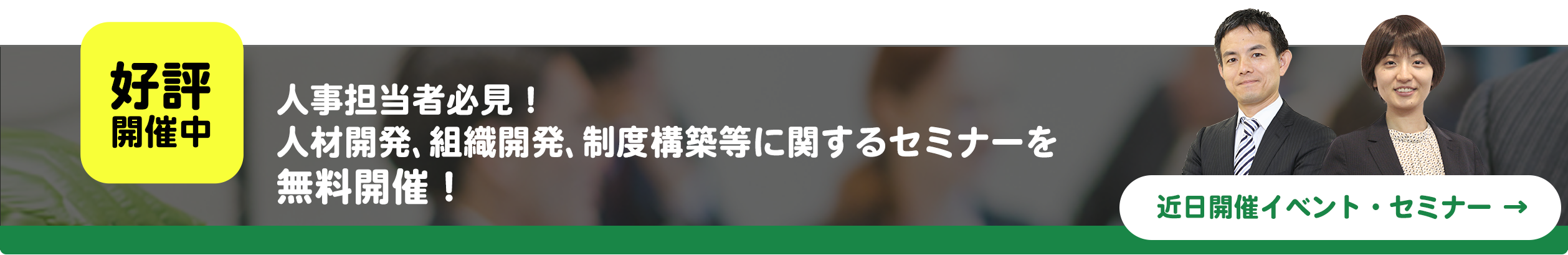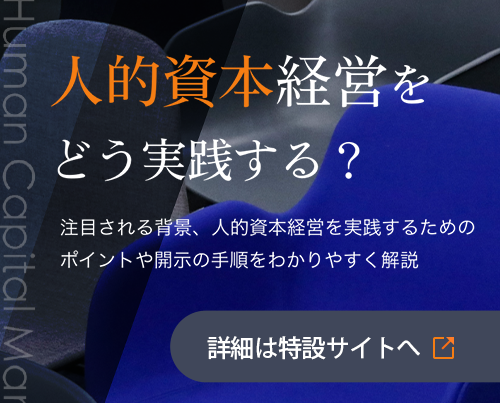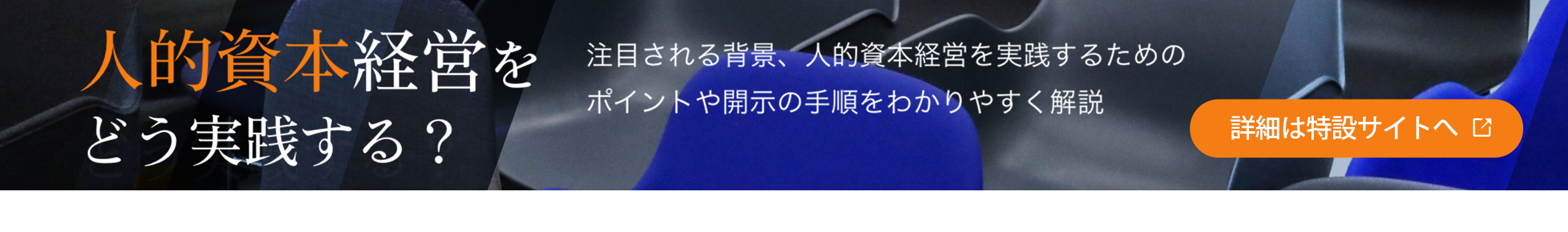2023年6月に閣議決定された骨太の方針には、長期雇用が当たり前だった日本の雇用形態が変化しつつある状況を受けて、退職所得課税制度の見直しが盛り込まれています。見直しが行われた場合、退職金を受け取るときにどのような影響が生じるのでしょうか。こちらでは、退職金の税制見直しの背景などについて解説していきます。

現行の税制はどうなっている?
現行の退職所得課税制度では、退職金から退職所得控除分を差し引いた金額に2分の1を乗じたものが課税対象額となっています。
この内、退職所得控除額は勤続年数によって変化するようになっており、長期的に勤務するほど控除額も大きくなります。具体的な計算式は、以下の通りです。
勤続年数20年以下の場合:40万円×勤続年数
勤続年数20年超の場合:70万円×(勤続年数-20年)+800万円
つまり、勤続年数20年間は毎年40万円ずつ控除額が増えていきますが、20年を超えると毎年70万円ずつ控除額が増えていくことになります。例えば、20年間働いた場合の控除額は800万円ですが、その倍、40年働いた場合は控除額が2200万円と大幅に増える計算です。なお、1年に満たない端数の期間については、1年として計算します。つまり、19年3か月働いた場合も、20年ちょうど働いた場合も、同じ800万円の控除額です。
実際の課税対象額は、上記控除額を差し引いた残額のさらに半分になります。例えば、退職金が2000万円で勤続年数が25年の場合、2000万円-(70万円×(25-20年)+800万円)=2000万円-1150万円=850万円の半額、425万円に対して退職所得税が加算されます。
そして、退職所得税は累進課税ですので、課税対象額によって税率が変わってきます。令和5年分所得税の税額表によれば、1000円以下を切り捨てた課税退職所得金額が1000円から194万9000円までであれば課税対象額の5%、195万円から329万9000円までならば控除額9万7500円を差し引いた残額の10%、694万9000円までなら42万7500円を差し引いた残額に対して20%、899万9000円までなら63万6000円を差し引いた残額の23%、1799万9000円までなら153万6000円を差し引いた残額の33%、3999万9000円までなら279万6000円を差し引いた残額の40%、それ以上は控除額479万6000円を差し引いた残額の45%が納付すべき退職所得税です。
このように、退職所得は通常の所得税よりも控除が大きく、納税額が抑えられていることが分かります。

退職所得課税見直しの背景
そもそも、なぜ今回、退職金の税制見直しが骨太の方針に盛り込まれたのでしょうか。その背景には、日本企業の雇用形態の変化にあると考えられています。元々、現行の退職所得課税制度が実施されていたころは、従業員の企業に対する忠誠心が高く、年功序列制度で同じ会社に長期間勤務するほど役職に就きやすく、収入も増える傾向が見られていました。
実際、1967年の政府税制調査会による「長期税制のあり方についての中間答申、税制簡素化についての第一次答申、昭和42年度税制改正大綱についての答申、昭和42年度の税制改正に関する答申」では、退職金は一時金の為担税力が弱く、所得税の累進性を軽減する目的からも退職所等控除の引き上げが望ましいと記載されています。永年勤続者や長期勤続者が優遇される税制にすることで、定年まで働けば所得控除額が大きくなるようなシステムにしていたのです。
しかし、近年では老後2000万円問題でもみられるように、老後の生活費を年金だけで賄うことが難しく、60歳の定年後でも働く意欲を持つ勤労者が増えています。また、スキルアップやキャリアアップ、待遇の改善などを目指して気軽に転職する労働者の割合が高くなっており、従来のように、定年退職するまで同じ企業で働く意欲がある労働者が減少してきました。
そして、政府の立場からも、従来の長期間勤続すればするほど退職金の控除額が増える現状の税制では成長産業への転職がしづらくなるのではないかという懸念が出ています。
その結果、他業種への転職の足かせになるような現状の退職所得課税制度を廃止して、新たなルールを決めることで、今までよりも気軽に転職できるような環境づくりを目指しているというのが、退職金の税制見直しを公表するに至った背景にあります。
退職金課税は見直しでどう変わる?
では、2023年骨太の方針で公表されている通り、退職金の税制見直しが行われた場合にはどのように変わるのでしょうか。これについては、2023年骨太の方針においても具体的な見直し後の予定が公表されているわけではありませんので、正確な内容を紹介することはできません。しかし、労働移動の円滑化を目指している政府の方針からある程度の推測をすることは可能です。勤続年数が転職を決意する際の足かせにならないように、退職金の控除額が勤続年数に影響を受けないような内容にすると考えられるでしょう。
具体的にどのような内容にするかは、慎重な議論が必要であるため、すぐに公表される予定にはなっていません。ただ、上記のような意図があると考えた場合には、退職所得控除額を一定にすること、転職した場合でも勤続年数を通算できるようにすることなどが考えられます。
退職所得控除の一律化を実施する場合には、勤続年数に関わらず、勤続年数1年あたりにつき同じ控除額を乗じていくことになるでしょう。とはいえ、1年あたりの控除額をどうするかは未知数です。例えば、一律50万円にした場合、勤続年数が20年以下の労働者にとっては退職所得の控除額が当初より大幅に増額されるため、大きなメリットとなり得ます。しかし、20年以上勤務している人は、長期間同じ企業で働けば働くほど、従来の退職金控除よりも金額が少なくなってしまうため、デメリットにしかならないでしょう。
一方で、勤続年数の通算が可能になった場合、転職先に以前の職場からの勤続年数を引き継げるようになりますので、退職金を気にせずに転職ができるだけでなく、長期勤務による退職所得控除の恩恵を受けられる可能性も生じます。
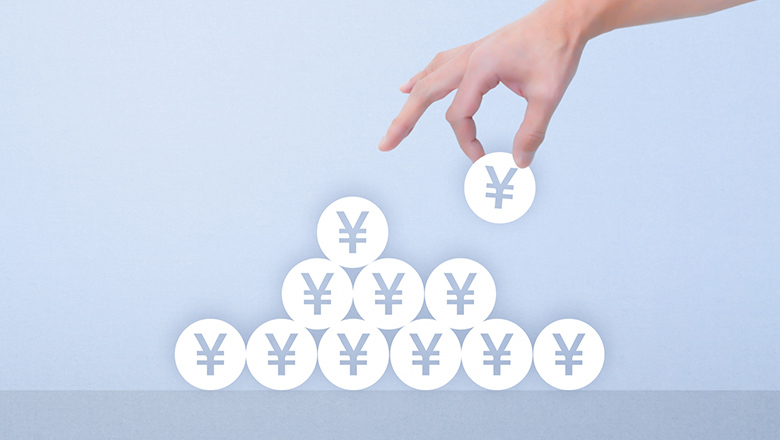
退職金の税制見直しで予想される影響
退職金の税制見直しが実際に行われた場合、どのような影響が発生するのでしょうか。まず、勤続年数による退職所得控除の優遇を止めた場合、勤続年数1年あたりの控除額が40万円のままであれば、勤続年数20年以下の人には影響がほとんどないでしょう。一方で、勤続年数20年超の人は、控除額が減額となり、実際に受け取ることができる手取り額が少なくなる可能性があります。
これは、従業員だけでなく、iDeCoに加入している人でも同じです。iDeCoは拠出金を年金として受け取るか、退職金として受け取るか選ぶことが可能です。ここで退職金として受け取る場合には、拠出期間=勤続年数として退職金の計算をされてしまいますので、長期的に拠出していた人は退職金の手取りが少なくなるかもしれません。
一方で、勤続年数の通算が可能になる場合には、転職を前向きに検討する従業員が増える可能性があります。急激に転職希望者が増えた場合、企業は退職手続きや求人の申し込み、面接などの通常業務以外の負担が増えることもあるでしょう。仕事に慣れているベテランの従業員が大勢転職した場合、企業にとっても少なくない損失になりますので、普段から従業員の要望を聞き取り、可能なものは取り入れるなど、定着率の高い職場を目指すことも必要です。
退職金の税制見直しについては今後の情報にも注目を
退職金の税制見直しについては、現時点で具体的な内容が公表されているわけではありません。しかし、成長産業への転職を推進するという背景がある以上、長期雇用の従業員への影響が大きいことは予測されるでしょう。企業としては、最終的にどのような見直し内容になるのか、今後も新たな情報に注目しておく必要があります。
この記事を読んだあなたにおすすめ!